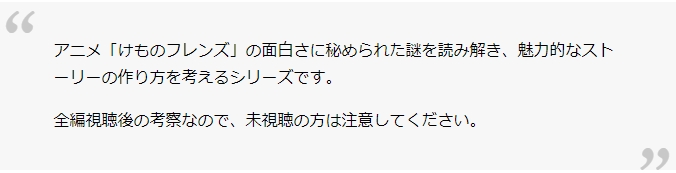
【Bパート 食材を調理してこその料理】
かばんちゃんとサーバルによる料理づくりがスタートします。2人は用意してあった料理の本を眺めていましたが、そこで博士が調理開始の号令をかけました。
アフリカオオコノハズク(博士):それではスタートです。
サーバル:えっ?
かばんちゃん:えっ?
博士:この砂がなくなるまでに調理して、我々がおいしいといえばお前が何の動物か教えてあげるのです。
ワシミミズク(助手):ついでに、副賞もつけるですよ。
サーバル:よーし!やるぞー!
かばんちゃん:うん!
かばんちゃん:うーん。(本を読みながら)
サーバル:わかりそう?
かばんちゃん:うん、食材によってできる料理が違うんだって。
サーバル:じゃあ、まず何があるか見てみようか。・・・うわー!いっぱいあるね!
かばんちゃん:食材って、どこから持ってきたんですか?
助手:ジャパリまんの原料を作る畑があるのです。そこからちょいです。
博士:ちょいちょいです。
サーバル:このままでも、ハムッ!(バナナを食べる)食べられるんじゃないの?
助手:何らかの手が入って、初めて料理なのです。
博士:手が入っていないものなど、我々なんの面白みもないのですよ。
サーバル:大変だね。なんでそんなことするんだろう?
「時間の概念」が登場
6話のメインテーマである「料理づくり」がスタートしました。ここで博士と助手は「砂時計」を用意し、制限時間を設けました。時間の概念が登場するのも、けものフレンズの劇中では珍しいシーンです。
今まで時間の概念を表す演出としては、「来週合戦がある」と語っていたライオンなどが挙げられますが、それ以外のフレンズたちは特に時間に言及することもなく、日々適当に過ごしていることがわかります。「時間を意識している」という点においても、やはり博士と助手は特別なフレンズであるということがお分かりいただけるでしょう。
なお、細かいことですが、助手が「かばんちゃんが何の動物か教えるだけでなく、副賞もつける」といっていますが、この「副賞」が後のストーリーに大きな影響を与えます。
意気込みよく料理の本を読み始めたかばんちゃんですが、すぐに重要な事実に気が付きました。それは「料理は組み合わせる食べ物の種類によってできあがるものが異なる」という点です。
普段料理を食べている我々人間からすれば当たり前の話ですが、彼女たちフレンズは日常的にジャパリまん以外食べていないということを忘れてはいけません。そんな当たり前のこともわからないくらい、フレンズにとって料理とは縁遠いものなのです。
ジャパリまんの製造過程がついに判明
かばんちゃんと違い、文字が読めないサーバルはここで先に料理を確認しようとしています。これはサーバルにしては(失礼)非常に良い判断です。かばんちゃんの読んでいる本はイラスト(写真)付きであり、文字の読めないサーバルであっても見た目で何の材料があるか確認しておくことはできるでしょう。
かばんちゃんも、重要な事実に気が付き博士たちに質問しました。それは、「材料は一体どこから調達してきたのか?」ということです。野菜は一部を除き、人工的に作られた植物ですから、自然界には存在しません。どこか管理された農場のようなところで計画的に作られているのでなければ、いくら博士や助手といえども入手することは不可能なはずです。
博士と助手はこれに対し、「ジャパリまんを原料を作る畑から持ってきた」と応えています。これは単にかばんちゃんの質問に対する回答になっているだけではなく、ジャパリパークの謎を解くという意味からも重要な発言です。
フレンズたちが基本的にジャパリまんを食べているのはわかっていたことですが、ジャパリまんについては未だに謎が多く残っていました。そのひとつが、「どこで作られ、どのように配給されているのか」という点です。今回の回答でその謎のひとつが解決したことになります。
もちろん、「すべてのフレンズが食べる量を賄えるのか?」、「パーク中にいるフレンズたちにどのように作ったジャパリまんを配給しているのか?」、「そもそもジャパリまんはどうやって作っているのか?」といった謎はいまだに残っています。これについても、後々ヒントになる情報が出てくるかもしれません。
材料を食べるだけでは博士たちの悩みは解決しない
サーバルは「材料をそのまま食べてもいいのではないか?」と料理にこだわる博士たちに疑問を呈します。このとき、サーバルがかじっている材料が何なのか劇中では特に触れられていませが、後に「バナナ」出会ったことが判明しています。詳しくは下記のリンクを参考にしてください。
http://kemono-friendsch.com/archives/20292
博士と助手は「手が入っていないものは料理とはいえず、何の面白みもない」と回答しています。料理のことをまったく知らないサーバルは、それでも2人の意図を理解できなかった様子ですが、このセリフも重要なことを示唆しています。
博士と助手の悩みが「特殊」である理由
それは、博士と助手が料理を食べたいと望んでいる理由です。2人は単なる知的好奇心から料理を食べたいと考えているわけではなく、ジャパリまんを食べ飽きている=退屈しているという点が動機に強く結びついているのです。
これまで登場してきたフレンズたちも「フレンズ化に伴う体の変化」になんとか対応しようと四苦八苦しており、それがストーリーのひとつのテーマになっていました。「仲間を作りたい」と望んでいたアルパカ・スリやトキ、「体にあった家」を欲していたアメリカビーバーとオグロプレーリードッグ、「体と能力に合わせて、安全に戦いを楽しむ方法」を知りたがっていたライオンやヘラジカなど例は山ほどあります。
博士と助手の望みは、彼らとは少し方向性に異なる部分があります。彼女たちが「フレンズの体でなければ食べられないものを食べたい」と望んでいることは事実ですが、それならサーバルが言うとおり「今の体でないと食べられない食材を探してそれを直接食べる」という解決策もあるはずです。
しかし、博士と助手はそうした方法を選びませんでした(あるいは、過去には試したこともあるのかもしれませんが)。それだけでは飽き足らず、料理というヒトの文化を自分たちで試したいと考えているのです。
ですが、彼女たちには自分で料理ができない理由があり(これは後ほど判明します)、ずっと「料理を作れる存在を待ち望んでいた」という背景があるわけです。
博士と助手は、かばんちゃんをずっと待っていた
このように、博士と助手の望みは次の部分でほかのフレンズの望みと異なっています。
1.望みを叶える方法をすでに知っている
2.自分たちではその方法を実行できないため、「実行できる存在」を待ち望んでいる
ビーバーは、「フレンズの体に合う家」をいかにしてつくったらいいか(手順だけは見えていたとはいえ)、その方法に自力で気がつくことはついにできませんでした。この点についてはライオンやヘラジカなど、ほかの悩みを抱えていたフレンズたちも同様です。
「料理を作って食べる」という具体的な解決法に自力で辿りついたのは博士と助手だけです。
また、彼女たちは自力でその方法を実行することはできなかったとはいえ、「どんなフレンズなら、自分たちの望みを叶えてくれるか」を理解しており、ずっとその存在を待っていました。言い換えると、「博士と助手はかばんちゃんが図書館にやってくるのをずっと待ち続けていた」ということになります。この事実は後々極めて重要になるので、よく覚えておいてください。

