2025年1月17日に全国の劇場で公開された『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』。
特別映像が追加されたものを含めて、私は劇場に5回足を運びました。4月のTVシリーズ放送開始を前に、作品の内容に対する私の考察と、今後の展開の予想を以下にまとめます。
元ネタはコレか?:高い城の男
ガンダムはSF作品です。往々にして、新しいSF作品が生まれるときは、それよりも前に出たSF作品が「元ネタ」になることも少なくありません。そう考えてジークアクスの元ネタになっていそうな作品がないか調べてみたところ、私が最もその可能性が高いと考えた作品が「高い城の男」でした。
第二次大戦のIFを描いた「高い城の男」
「高い城の男」は、SF作家フィリップ・K・ディックによる小説で、第二次世界大戦で枢軸国が勝利した世界を舞台にした物語です。
【ストーリーの概要】
- 第二次世界大戦で連合国が敗れ、日本とドイツが勝利し、アメリカの東側・西側を占領した世界
- 東洋の占術(易経)が流行していて、複数の人物が易経を指針として行動している
- 日本が支配するアメリカ西海岸では、「もしも連合国が枢軸国に勝利していたら」という歴史改変小説「イナゴ身重く横たわる」が流行している
「高い城の男」は、SFというジャンルの中で最も有名な「仮想戦記」の一冊であり、本来は「連合国が勝利するはずの第二次大戦で、枢軸国が勝利している」という世界が舞台です。本来は「連邦が勝利するはずの一年戦争で、ジオンが勝利している」という世界が舞台になっているジークアクスと、世界観の設定を見るだけでも大きな共通点があります。鶴巻監督はジークアクスを「宇宙世紀の仮想戦記もの」と表現しています。よくファンの間で語られる「パラレルワールド」という表現は、鶴巻氏本人は用いていないようです。
ここからは「高い城の男」とジークアクスに垣間見える共通項から、この物語を通して伝えようとているテーマを考察していきます。
流出画像に見える「高い城の男」の痕跡
こちらは、ジークアクスのイタリア語公式サイトから流出したとされるジークアクス初期企画の資料の一部です。これを見ると、ジークアクスの機体名称が「ガンダム・ライズヘビー」となっており、「イナゴ身重く横たわる(The Grasshopper Lies Heavy)」との関連性を強く示唆する内容になっています。
「本物」へのマチュの憧れ
コロニー生まれの私たちは、本物の重力も、本物の空も知らない。もちろん、本物の海も。
機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-
本作では本物・偽物というワードが繰り返し登場し、物語のテーマになっていることが示唆されています。例えば、カネバン有限公司を訪れた際、アンキーからニャアンの制服が偽物だと指摘されるシーンでは、マチュが「本物のJK」、ニャアンが「偽物のJK」として描かれています。
主人公・マチュはコロニーで生まれ育った自分たちの暮らしを「偽物」と感じ、重力・空・海といった「本物」の感覚に強い憧れをいだいています。彼女の持ち物の多くが海洋生物のモチーフを使っていることからも「本物の海」への憧れが伺えます。彼女が経験する「キラキラ」は海のイメージと強く結びついて表現され、マチュの内面を象徴する重要な要素ともなっています。
これはデジタルツール・コンテンツの発達により、日常的には「本物」よりも、バーチャルな、擬似的な体験することのほうが多い現代人にも共感できるポイントではないでしょうか。
コンテンツという領域で見ても同様のことが言えます。たとえば『機動戦士ガンダム』の物語をリアルタイムで視聴していた人は、すでに一定の年齢に達しています。若い人は、アーカイブで視聴した人がほとんどでしょう。コンテンツとしては同じものを見ているわけですが、時代背景がまったく異なるため同じ視聴体験をしているとは言えません。アニメファンの中には「自分たちが見ている『ガンダム』は、当時の人達が見たものと同じものなのか?」といった感覚を持っている人もいると思います。
高い城の男で描かれる「本物と偽物」
「ある品物の中に歴史があるってことさ。いいかね、この二つのジッポー・ライターの片方は、フランクリン・D・ローズヴェルトが暗殺されたとき、そのポケットに入っていた。もう一方は入っていなかった。つまり、片方には史実性がある。どっさりある。品物としてこれ以上は持てないぐらいにある。だが、もう一方はなんにもない。それが感じられるかね?」老人はリタをつついた。「感じられはせん。どっちがどっちか、見分けもつかん。そこにつきまとう〝神秘なプラズマ的存在〟や〝霊気〟──そんなものはなにもない」
フィリップ・K・ディック. 高い城の男 (pp.94-95). 株式会社早川書房. Kindle 版.
本物と偽物は、「高い城の男」のテーマでもあります。劇中では「美術品の模造品」や「偽の肩書を名乗る人物」などが複数登場します。
そうしたモチーフの中でも、最大の意味合いを持つアイテムが、作中作である『イナゴ身重く横たわる』です。これはある小説家が、易経による託宣に基づいて書いた小説という設定です。「なぜ物語を作らせたのか?」と、登場人物の一人が易経で占うと「真実だから」という託宣が出る、というところが物語のクライマックスになっています。
「それは、つまり、ぼくの本が真実ということなのか?」 「そうです」 怒りをこめて、彼はいった。「ドイツと日本が戦争に負けたというのか?」 「そうです」
フィリップ・K・ディック. 高い城の男 (pp.386-387). 株式会社早川書房. Kindle 版.
この事実を知った登場人物たちは皆困惑し、どう解釈したらいいのかわからないまま物語は終幕を迎えます。
どうすれば自由になれるのか?
宇宙って、自由ですか?
機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-
「本物と偽物」以外に明示的に作中で示されているテーマが「自由」です。
自由の意味を探るマチュ
カネバン有限公司を訪れたマチュが、初めてクランバトル用のザクを見て「宇宙って、自由ですか?」と問いかける場面は、彼女の純粋な自由への憧れを象徴しています。
社会の現実と個人の自由
その後、ジークアクスと赤いガンダムがコロニー内に乱入し、軍警が介入する事態に発展します。この混乱は難民街にまで及び、被害が広がります。
この状況下でアンキーが発する「ジオンが戦争に勝ってもスペースノイドは自由になれない、いつまで経っても苦しいままだ」という言葉は、先ほどのマチュの質問に対する、より広い視点からの回答となっています。
ここで興味深いのは、マチュとアンキーの「自由」に対する解釈の違いです。マチュは個人の意思決定という観点から自由を捉えていますが、アンキーは社会問題という大きな枠組みでの自由という意味合いで、それに回答しました。この対比は、作品が伝えようとしているメッセージの核心を示唆しているように思えます。
つまり、『ジークアクス』は「個人が自由になろうと思ったら、社会問題を解決しないといけない」というテーマを内包しているのではないでしょうか。さらに踏み込んで考えれば、「個人が自由になることで、社会も自由になる」という可能性も示唆されているように感じられます。
訓練を受けたわけでもないマチュが、何の苦労もなくオメガサイコミュを起動し操縦桿を握ることもなく思い通りに動かせるという描写は、まさに「自由」そのものです。マチュはガンダムに乗り、そして宇宙に出て戦うことで初めて自由を手にすることができる、という点が明示的に描写された演出だといえます。この点は「スペースノイドが自由を得るために戦う」という、従来のガンダム作品のテーマの一つとも合致します。
人々に自由を与える「架空戦記」
「あのご本の中には」とジュリアナはいった。「一つの出口が示されています。先生の真意はそれじゃないんですか?」 「〝出口〟ね」アベンゼンは皮肉な口調でくり返した。 「先生はあたしに大きなものを与えてくださいました。やっとわかったんです。この世界にあるものをなに一つ恐れてはいけないし、欲しがったり、憎んだり、避けたりしてもいけない。逃げる必要もないし、追いかける必要もない」
フィリップ・K・ディック. 高い城の男 (p.381). 株式会社早川書房. Kindle 版.
「高い城の男」で人々を「自由」に導いてくれるアイテムが、日本やその統治地域を中心にベストセラーとなっている作中小説「イナゴ身重く横たわる」です。劇中の歴史=枢軸国の勝利とは異なる歴史(=連合国の勝利)を辿った世界が描かれる小説にふれることによって「その世界の常識」に縛られて、知らず知らずのうちに自身の選択肢を狭めてしまっている人々に対して、気づきを与える効果を生み出しています。
たとえば、劇中ではアメリカ太平洋側は日本に占領されているため、現地で生きるアメリカ人は日本人にへりくだり、おべっかを使わなければならない状況に置かれています。そのため「自分たちは日本人に比べて劣っているのではないか」「不満があっても、彼らの機嫌を損ねてはいけない」という意識に支配されている人がほとんどです。
日本人やドイツ人に頭を下げ、自分たちは到底彼らには及ばない、従うしかない、という常識をインプットされている衛星国や植民地の人々も「本当の歴史では自分たちは勝っていたんだ」と知れば、誇りと自信を持って振る舞えるようになるでしょう。
そういった人々が「イナゴ」に触れることよって目覚め、少しずつ行動を変えていく、縛られていた意識が変わっていく、という点が作品を通した一つのテーマになっています。
マチュから「自由」を奪っていたもの
主人公であるマチュは、大勢が見ている前で下着を丸出しにしながら逆立ちしたり、思いつきで学校を早退するなど、一見かなり「自由」に振る舞っているように見えます。
しかし、実際にはカネバン有限公司の面々から最初は「子ども」として見られ、まともに相手にされません。親から塾に通わさせられているものの、内心は不満に思っている様子も見られます。一見、裕福な人々が多く住まうサイド6で恵まれた生活を送っているようであっても、さまざまな束縛に囚われて不自由を感じていることが見え隠れしています。
注目すべきは、マチュはこうした状況に遭遇したとき、不満に思っていることは表情やリアクションから伺えるものの、相手に言い返すなど具体的な言葉で気持ちを表現することはない、という点です。これは視聴者、特に若い女性がマチュに感情移入しやすくするために、鶴巻監督が狙ってそうしている演出だと考えられます。セリフとして、マチュに何かを喋らせてしまった時点で、そのセリフに「のれる・のれない」が見る人の性格によって分かれてしまうことになるからです。
「フリクリ」や「トップをねらえ2!」など、過去の作品を見ても同様の演出傾向が見られます。ただ、最後までこの状況が続くわけではなく、どこかで「自由」を得るために自分の意思をはっきり周囲に示す展開が必ずやってくるでしょう。「高い城の男」で、「イナゴ」によって目覚めた人々が意識や行動を変えていったように。
戦勝国と中立国、そして難民
そして「その世界の常識」に縛られていた意識・行動を自由に解き放っていくのは、おそらくマチュだけではないでしょう。難民出身であり、生きることに精一杯なニャアンや、ニュータイプでありながら散々な目にあっているエグザべなど、他のキャラクターたちも「自由」を得るために行動し、自信と誇りを取り戻す展開が必ずでてくるはずです。難民出身である彼らを始め「敗戦国となった連邦や虐げられている難民たちがどのように自信と誇りを取り戻すか」を描くエピソードも今後登場するのではないでしょうか。
戦勝国であるジオンを含め、ほとんどのキャラクターは「世界の常識」に行動を縛られているものの、マチュやシュウジ、シャアとシャリアにアンキーといった面々は「常識」からある程度自由な発想で行動するキャラクターとして描かれています。彼らの大半がニュータイプである、という点も偶然ではないでしょう。
富野由悠季が描きたかったニュータイプとは?
ガンダムという作品を扱う以上「ニュータイプ」の描き方について考えることは避けては通れません。
一旦「高い城の男」は脇にどけて、ジークアクスにおいて「ニュータイプ」「サイコミュ」などがどういった意味合いを持っているのか考えてみたいと思います。
そのためにはまず「機動戦士ガンダム」シリーズを生み出した富野由悠季氏が伝えたかったことはなにか?考えながら「ジークアクスはそれにどのような回答を出そうとしているのか」について考察していきます。
まず「富野由悠季が考えるニュータイプ」と「逆襲のシャアで何が示された(もしくは、示そうとされたのか)」について確認してみましょう。以下の動画でわかりやすく解説されているので、考察にあたってはこちらを参考にさせてもらいました。
以下、少し長いですが、動画の要約です。
【ガンダムのテーマ】
・ガンダムのテーマは「ヒトは変革できるのか」だった
・その表現手段として「ニュータイプ」という概念が生まれた
・人類が宇宙に進出すれば、そこに適応するためにヒトは変われる
・逆に「宇宙に出られない人=地球の重力に魂を惹かれた人々」は変われない
【ガンダムZZの初期プロット】
・シャアの目的は人類全体をニュータイプにすること
・そのために、地球に残った人々を強制的に宇宙に移民させようとした
・ジュドーはシャアの考えに反発
→「強制的に宇宙に出るのでは、ヒトは変われない。自らの意思で宇宙に出て、初めて変わることができる」と説く。
・このジュドーの思惟が地球に残る人々に伝播し、人々は自分の意志で宇宙に出ようと決意する、というストーリーになるはずだった
→この「ZZ」の初期プロットは、見せ方を変えて「逆襲のシャア」に引き継がれる。
【逆襲のシャアのテーマ】
・アクシズ・ショックは「地球を守ろうとするヒトの意志」が起こした
・アムロは「ヒトの意思は奇跡を起こせる」=ヒトは自らが変わろうと思えば変われる、ということを示そうとした
・地球に残る人々もアクシズ・ショックによる「ヒトの心の光」を見る、
・初期案(≒小説「ベルトーチカ・チルドレン」)では、上記の通り「ヒトの意思が奇跡を起こす」ストーリーになるはずだった
・しかし、出資者から「それだとモビルスーツの否定になる」という批判があった。
・そこで「サイコフレーム」という「奇跡を起こすキーアイテム」が登場することになった。
「ヒトの変革」を描ききれなかった挫折
特に重要なポイントは「富野氏は『ヒトは、自らの意思で変わろうとすれば変われる』という物語を描こうとしていたのに、サイコフレームというアイテムで奇跡が起きた、という話に変わってしまった」という点です。
実際、富野氏がこれ以降に作った「F91」や「Vガンダム」では、ニュータイプこそ登場するものの、サイコフレームの技術を含めて、その存在感は小さく、ストーリーの中であまり重要な意味を付与されていません。
富野氏も「惑星を押し返すようなすごい奇跡を起こせる魔法のようなアイテムがあります!」という設定をベースにしたのでは、それ以上「ヒトは変革できるのか」というテーマを描くことはできなかったのでしょう。
鶴巻監督が考える「ヒトの変革」とは?
では「ジークアクス」では「ヒトは変革できるのか」というガンダムのテーマに対して、どのように向き合おうとしているのでしょうか?鶴巻監督はジークアクスの舞台挨拶において、次のように語っています。
鶴巻監督は、改めてニュータイプに言及。「富野由悠季(監督)さんのニュータイプの概念に関して、新しい解釈をしたい」と、本作ならではのニュータイプの在り方を説明してくれた。
https://www.famitsu.com/article/202502/32490
私は、鶴巻監督が考えるニュータイプ論は「能力ではなく、意思と行動によって定義づけられるもの」として描こうとしているのではないか、と考えています。
自ら運命を切り開く意思が「ヒトを変える」
ジークアクスにおけるニュータイプといえば、まず前半のシャアが挙げられます。シャアは赤い彗星の「感」に従ってガンダムを奪取。戦争の勝敗を一変させる程の影響を与えました。シャアの行動と決断からはリスクを恐れない積極的な姿勢が伺えます。
彼女は本能のおもむくままに行動し、自分の存在を表現する。彼女がここへやってきたのは、害をするためじゃない。それはたまたま彼女にとってそういう成行きだったんだ。ちょうど、天候がわれわれにとってそういう成行きであるように。
フィリップ・K・ディック. 高い城の男 (p.388). 株式会社早川書房. Kindle 版.
後半では、本編の主人公となるマチュがオメガサイコミュを起動したことで、ニュータイプの素質があることが判明します。マチュはシャア以上に、常識やリスクにとらわれず、自分の理性と本能に従って意思決定・行動をしている様子が描かれています。羅列しただけでも、普通ではまず躊躇するような行動をこれだけとっています。
- 学校のプールで逆立ちし、水中に落下
- インストーラーデバイスを、密輸品と知りながらも捨てなかった
- ニャアンをけしかけて難民街を訪れ、カネバン有限公司に行く
- 自ら軍警に戦いを仕掛け、乗ったこともないMSに乗り込む
- たまたま発見したジークアクスに乗り込みコロニー外へ、軍警のザクを撃破
- 「キラキラ」のストリートペインティングに気が付き学校を早退
- ニャアンとシュウジを誘ってクランバトルの世界へ
シャアとマチュ、2人の相棒(MAV)も例外ではありません。
シャリア・ブルは、1年戦争のころはそこまで極端な行動は目立ちませんでしたが、戦後は「上官の許可も得ずにオメガサイコミュを使用する」「エグザべを奪還するために強硬な手段を取る」といった積極的な手段を取っています。
シュウジはマチュと出会う前から赤いガンダムに乗り、各地で戦闘を繰り返していた様子ですし、コロニー外壁にまで「キラキラ」のペインティングをして、軍警に追い回されていました。リスクや常識に縛られていたのなら、こんな行動はまず取らないでしょう。
彼らに共通するのは、常識にとらわれず直感を信じ、「運命を切り開こうとする強い意志」です。ジークアクスにおける「ヒトの変革」は、こうした描写を中心に描かれるのではないかと予想します。
鶴巻監督が考える「ニュータイプ」とは
富野氏が「ヒトの変革」を描ききれなかった理由は「ニュータイプの思惟が人々に伝播することで、全人類が自らの意思で地球から宇宙への移民を決意する」という展開にするはずが「サイコフレームという不思議なアイテムがニュータイプの力を増幅して、アクシズを押し返した」という話になってしまったからでした。
もし鶴巻監督が描こうとしている「ヒトの変革」が「自らの意思で変わろうとすれば、ヒトは変われる」「それを実践できる存在がニュータイプ」というものだとしたら、シャアやマチュのキャラクター像があのように描かれている点にも納得がいきます。
「ヒトの変革」にニュータイプやサイコミュは不要?
さらに「変わろうとする意思」が重要なのであれば、それはニュータイプの直感や「共振」などの特殊な能力や、サイコミュなどのテクノロジーも究極的には不要である、ということになります。それらは「変わろうとする意思」に目覚めるためのキーにはなっても「それがなければ変わることができない要素」にはならないはずだからです。
シャアやマチュ、シャリアなどのニュータイプは、直感力や洞察力に優れている描写はたしかに描かれていますが、それ以上に「自分が正しいと思うことを貫く」「他人を思いやる心」といった資質を持っている、という点も印象的に描写されています。
マチュはニャアンがカネバン有限公司のインターホンを鳴らそうとして躊躇しているとき、一切ためらわず代わりににそれを押します。その後、軍警に破壊される難民街を見て、悲しそうなニャアンの表情を見たことが、戦いに身を投じるきっかけになりました。
シャリアは、ジークアクスを失い責任を感じるエグザべを責めることもなく、傷を負った彼のために絆創膏を差し出す思いやりを見せました。
彼らの魅力はニュータイプとしての能力や、機動兵器を扱う戦闘力ばかりではありません。むしろ、こうした、それ以外の「人間的な資質」こそが「ヒトの変革」に至るハウツーを示すにあたって重要な要素である、ということを、鶴巻監督は描きたいのではないでしょうか。
人々の意思決定をサポートする「易経」
こうした「己の運命を切り開こう」とする描写は「高い城の男」においても見られます。
- 仕事を辞め、リスクを承知で未知の起業に挑戦する
- 評価が定まっていない新しい装飾品の販売に挑戦する
- 自分を事件に巻き込んだ他国の高官に危険を承知で啖呵を切る
- スパイと戦い、ターゲット担っている人に危機を伝えに行く
劇中の人物たちが、これら積極的な意思決定・アクションを繰り出す際、きっかけとなるアイテムが「易経」です。日本の占領地域を中心に、人々の多くが易経の託宣を深く信じており、重要な決断をするときには必ず易を占う様子が繰り返し描かれます。
言うまでもなく占いですから、その結果に科学的な根拠はありません。しかし、易を頼りにしている人々は、託宣の結果に宇宙の真理が反映されていると信じています。ちょうど、ジークアクスでニュータイプが、特に根拠のない自身の「感」に従い、その決断が自分にとっていいものだと信じて疑わず意思決定をするのと構造的によく似ています。
ニュータイプを導くメカたち
この易経に相当するような存在がジークアクスにもないか考えてみると、ハロや「赤いガンダム」などのメカが、人の意思決定をサポートする様子が思い出されます。
初めてカネバン有限公司を訪れたマチュが「空って、自由ですか?」とつぶやいたとき「ジユウ!ジユウ!」と応えたのはハロでした。その後も、インストーラーデバイスの挿入位置を教えたり、シュウジを「本物のMAV」と表現するなど、マチュがジークアクスに乗って戦うことを促しているような動きが見受けられます。
シュウジも、詳細は不明ながら「戦え、とガンダムがいっている」と語っているように、ガンダムから何らかのメッセージを感じ取っているような描写が見られます。
「キラキラ」やゼクノヴァを引き起こすサイコミュ
こうした、ジークアクスに登場する「人を導くメカ」の最たるものはサイコミュでしょう。サイコミュはニュータイプ同士の感応=「キラキラ」、そしてゼクノヴァを引き起こすキーアイテムでもあります。
さらに、シャアのゼクノヴァとともに、グラナダから消失したとされる「シャロンの薔薇」は謎めいた存在です。「キラキラ」、サイコミュ、そして「シャロンの薔薇」・・・、これらの正体を探るヒントが「高い城の男」にないか考えてみました。
「高い城の男」の幻の続編
「キラキラ」に近い現象は「高い城の男」では明示的には描かれていません。しかし、同じフィリップ・K・ディックの作品である「ヴァリス」にヒントが隠されています。未完に終わったものの「高い城の男」には続編の構想があり、それは部分的に「ヴァリス」という作品に生かされているというのです。
このことが紹介されているのが、以下の動画です。こちらは私と同様、ジークアクスが「高い城の男」のストーリーを下敷きにしているのではないかと考えている方が公開しているジークアクスの動画で、本記事の制作においても大変参考にさせてもらいました。興味深い内容なので、ぜひ一度見てみてください。
「ヴァリス」で描かれる「キラキラ」体験
上記の動画(1本目)では「高い城の男」の続編構想と「ヴァリス」の関連について言及があります。
Wikipediaから「ヴァリス」のストーリーを見ていくと、ジークアクスとも関連が深そうな内容を見つけました。
1971年カリフォルニア。主人公のSF作家ホースラヴァー・ファットは、友人の自殺を切っ掛けに現実を喪失しはじめる。薬物依存と精神衰弱の果て、ついに、1974年3月、ピンク色の光線を額に照射される(と主人公ファット自身が解釈した神秘体験をする)。ピンク色の光線は、ファットにとって神的啓示を含む高密度情報として知覚され、そこで得た情報の一部にもとづき、現実に息子の先天的疾患を発見する(してしまう)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%B9_(%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BBK%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
この「ピンク色の光線とそれによる神秘体験」の描写は、ジークアクスにおける「キラキラ」そのものではないでしょうか?
「キラキラ」はこの世の真理に触れること
「ヴァリス」では、ピンク色の光線は「この世の真理の一端に触れる神秘体験」として描かれており、それを解析した宗教団体が「この世の真理を完全に理解できる存在=神」を誕生させることに成功した、というストーリーが展開されています。
しかし、ある映画……作中(同名)映画『VALIS』(エリック・ランプトン作)……を観たことで事態は変容する。同映画にはサブリミナル効果と暗号によるメッセージが隠されていた。ファットが独自のものと考えていた自らの神学と同じ情報の源泉に触れた人間にしかわからない(VALISからのピンク色の光線を照射された者にしかわからない〈とされる〉)メッセージを直感し、友人たちと同映画を制作した小さなカルト団体を訪れる。
そこでは3人の団体員が、怪しげな研究と実験に耽っており、なにやらVALIS(ここでのVALISの意味は、グノーシス的牢獄宇宙に派遣されたキリスト精神の意味に変容する〈詳細には三位一体のうちの聖霊としての意にさらに変容する〉)の理解に到達し、さらには、真の神を誕生させることにも成功したと語る。そして、救世主,キリスト,神などといった称揚とともに、ファットたちをついにその真の神と邂逅させる。
それはソフィアと名付けられた一人の少女だった(必ずしも人間の少女ではなく、少女型AIとも、少女型の神だとも推理がなされるが明示的ではない)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%B9_(%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BBK%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
これがジークアクスにおける「キラキラ」と同じ意味を持つのであれば、なぜマチュがあれほど「キラキラ」に惹かれたのか納得できます。マチュは何よりも「本物」を求める強い気持ちを持っていました。その彼女が「宇宙の真理」に触れる体験をしたのであれば、それ以上ない説得力を持って「本物」だという実感を得ることができたでしょう。
「もっとあのキラキラを体験したい」という強い動機に突き動かされてクランバトルの世界へ入り込んでいくのは疑いありません。おそらく、シュウジも同じような動機で赤いガンダムに乗っているのでしょう。
人々が「真理」の一端に触れる意味
実は「登場人物が真実の世界を垣間見る」という描写自体は「高い城の男」にも登場します。
そのために使われるアイテムが、エドフランク宝飾工房で作られる装身具です。主要キャラクターの一人であるフランクが、トラブルが原因で職場を退職。一念発起して起業した工房で作られたオリジナルのアメリカ製品、という設定です。
劇中のアメリカは日独に分割統治されており、アメリカの歴史に由来がある美術品などには価値があるものの「敗戦国のオリジナル製品」の価値はまったく評価されていない状態です。そんな中で、あえて自分たちの技術を信じてオリジナルの製品を作る、そしてその価値を信じて売るという過程を通じて徐々にアメリカ人が自信と誇りを取り戻していく、という展開が一つのハイライトになっています。
「真理」に触れる体験が人の意識を変える
ここはどこだ? おれの世界じゃない、おれの時空間じゃない。 あの銀の三角がおれを迷わせたんだ。もやい綱を解いたおかげで、空虚の上に立つことになった。
フィリップ・K・ディック. 高い城の男 (p.349). 株式会社早川書房. Kindle 版.
そのエドフランク宝飾工房の装身具を使い、登場人物の一人である田上(Tagomi)は、瞑想することによって「イナゴ」の世界=真実の世界を垣間見る、という体験をしています。
田上が一時的に迷い込んだ世界では、白人たちは日本人である自分を恐れず、逆に見下すような態度を取ります。この経験は彼に非常に大きなショックを与えました。そしてそれは、彼が元の世界に戻ってから取った行動に大きな影響を与えます。
ちょうど、田上がこの神秘的な体験をした前後、ドイツでは権力争いが起こっていました。日本を核攻撃しようとする派閥と、宇宙進出を加速させようとする派閥に分かれて、主導権争いが激化していたのです。
田上はこの争いに巻き込まれ、ドイツのエージェントとの銃撃戦にまで発展していました。とはいえ、まだどちらの派閥が勝つかわからない状況である以上、無難に考えるのならドイツとは表面的には対決せず、穏便に事件を解決するべきでした。
ところが、神秘的な体験を経た田上は、事件の後始末に来たドイツの高官に強気な態度を取ります。これも「真実の世界ではドイツは戦争に勝利していない」と彼が体験したことが引き金になっています。
鶴巻監督が言及した「キラキラ」
「キラキラ」が「高い城の男」や「ヴァリス」で描かれた神秘体験と同種のものであることを示唆していることは、鶴巻監督からも語られています。
劇場で発売されたパンフレット「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- “MATERIALS” 」によれば、キラキラのアイデアを出したのは、アニメ『機動戦士GundamGQuuuuuuX』の監督の鶴巻和哉。鶴巻はアニメ『機動戦士ガンダム』の第41話「光る宇宙」でアムロ・レイとララァ・スンが意識を交感するシーンを見て、このシーンが純粋な精神世界描写だけでなく、何かしらの現象も描いていたとして物理学的なものであれば、学術的な名称があるはずだという発想から、キラキラという設定を作ったのだという。アニメ『機動戦士ガンダム』の劇中ではその精神交感シーンが、物理的な現象なのかアニメーションの演出なのかハッキリとした言及はされなかったが、鶴巻は『GQuuuuuuX』においては、ハルシネーション(幻覚)という現象として描くことを明言した。
https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A9%28GQuuuuuuX%29
また、宇宙世紀のガンダム作品における「全体」概念との関連性も指摘されています。
キラキラは本来の宇宙世紀における高次元フィールドの全体との関連性が推察される。全体はアニメ『機動戦士Zガンダム』から導入された概念で、特殊な知覚を持った突然変異種であるニュータイプが見れる高次元のフィールドで、ニュータイプが本来なら知りえない情報を会得出来るのもこの全体の既知が流れ込むからだという設定である。
https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A9%28GQuuuuuuX%29
全体は、ニュータイプ(いずれ獲得する能力を先に得ていた人々)が力を引き出すことの出来る場(フィールド)であり、人間が死亡した際に発生する残留思念(思惟)が集っている。
https://dic.pixiv.net/a/%E5%85%A8%E4%BD%93%28%E5%AE%87%E5%AE%99%E4%B8%96%E7%B4%80%29
ニュータイプは「全体」により「他人の既知の伝播」や「刻」が見えるといった現象を体験できるとされています。
他人の既知の伝播
小説『不死鳥狩り』でヨナはフェネクスの近くにいた影響で、誰のものかも分からぬ他者の魂の既知が自分の既知と同化して、本来ならば知りえない対象の情報を獲得し、短期間でパイロットしての技術も向上した。 同作において、ニュータイプが急速に戦闘技能が上達していく理屈は、他者の既知が自分にインストールされるからという論法である。
刻
刻とは、この世界の歴史が保存されたアカシックレコードのようなものである。
ララァ・スンやシャア・アズナブルなど、死ぬ間際に「刻が見える」という台詞は印象深い。
『不死鳥狩り』によれば、高次元にある全体にとって刻は千年、万年、億年の時間が積層されようと、それを並列して見渡せるのだという。
https://dic.pixiv.net/a/%E5%85%A8%E4%BD%93%28%E5%AE%87%E5%AE%99%E4%B8%96%E7%B4%80%29#h3_0
まとめると、次のようになります。
- 「キラキラ」は「物理現象を伴うもの」として描かれることが鶴巻監督から明言されている
- 「キラキラ」は、Zガンダム以降の宇宙世紀ガンダムで描かれた「全体」との関連が見られる
- 「全体」とはニュータイプがアクセスできる場で、死者の残留思念が集まっている
- ニュータイプは「全体」とつながることで「他人の既知の伝播」や「刻」が見える体験をする
私は「キラキラ」は「高い城の男」や「ヴァリス」に見える神秘体験を、富野由悠季氏のニュータイプの設定と組み合わせる形で、鶴巻監督が着想したものと考えています。ゼクノヴァについてはもう少し秘密があると思っており、もう少し後で明らかにして行きたいと思います。
内輪もめするジオン・マチュは地球へ?
少し脱線しますが、ジークアクスにおける「ジオンの内輪もめ」も「高い城の男」と同じような展開になるのではないか、と予想できます。
前半の1年戦争パートは、ファーストの全43話の内容とほぼ同じ長さの物語を駆け足でたどる、という忙しないものでした。そんな限られた時間の中で、作品では「キシリアとギレンの対立」を繰り返し強調しています。例えば、劇中では以下のようなセリフがあります。
- “総帥がいう人の革新は口先ばかりだからな”
- “君がキシリア閣下とギレン総帥との間で板挟みならずに済むいい方法がある”
- “最初からビグザム一個戦隊を投入しておけば3日早く落とせたのだ。- しかしそれではギレン総帥に借りを作ることになります”
さらに2/22以降の劇場放映で追加された特別映像でも「ザビ家の内輪もめ」が起きていることが明言されています。
おそらく「ギレン派=再び連邦との戦争を目指す、重MA・大量破壊兵器重視の派閥」と「キシリア派=ニュータイプ・サイコミュ研究と、地球圏外部への進出を目指す派閥」とに分かれて争う、という展開になるではないでしょうか。
シャリア・ブル(ソドン)隊は、表面上はキシリア派に加担しつつ、シャアの捜索を続ける(もし、シャアが見つかれば新しい時代のために、ザビ家と戦うことを目指して)という展開になるのではないかと思います。
また、特別映像では以下の描写も見られます。
- 「シャロンの薔薇」は地球にある、とシュウジが示唆している
- それを探すために、シュウジは地球に行きたい(そのためにクランバトルをする)
- マチュも「私も行く」と明言
- シュウジが乗る赤いガンダムがゼクノヴァを起こしかけている
これらのことから「シュウジがゼクノヴァで消失、マチュは彼を探すためにソドンに同行し、地球に行く」という展開になるのではないかと予想します。
ゼクノヴァと「シャロンの薔薇」の謎
前編のラストでシャアが起こした謎の現象「ゼクノヴァ」、そして「シャロンの薔薇」とは一体どのようなものなのでしょうか?
ゼクノヴァは「逆襲のシャア」におけるアクシズ・ショックに酷似した現象として描かれています。
ニュータイプを人柱に人類の集団無意識がサイコミュによってエネルギーに転化された
https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%BA%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AF
ただ「逆襲のシャア」においてもアクシズ・ショックがどんな物理現象だったのかは明確にはされていませんので、そこを掘り下げようとする行為にはあまり意味がないと考えています。おそらく鶴巻・榎戸両氏の中にも明確な応えはなく、作中で描かれることもないでしょう。
「フリクリ」「トップをねらえ2!」においても超常的な現象が描かれますが、そのメカニズムが明確に示されることは最後までありませんでした。なので、現象として解明するよりも「物語の中でどんな意味合いを持っているか」について考えてみたいと思います。
ゼクノヴァは「シャロンの薔薇」が引き起こす
ゼクノヴァとアクシズ・ショックには、明確な違いが一つあります。アクシズ・ショックはアムロやシャアなど、作中で現場にいたニュータイプがきっかけとなって引き起こされましたが、ゼクノヴァはそうではありません。「サイコミュが反応している、私にではない」とシャアも明言していますし、現象が起きたとき「シャロンの薔薇」がグラナダの地下から消失した、というセリフからも「シャロンの薔薇」によって現象が引き起こされたとわかります。
ヒトを真理に導くメカたちの親玉
比較対象として、再び「ヴァリス」を取り上げます。
「ヴァリス」では、詳細な正体こそ不明なものの、一定の真理に到達した「神」のような存在の少女が登場します。そして、少女の導きにより主人公は「自分がこの物語の作者であった」ということに気がつく、という展開になっていきます。
訝しみながらも、ソフィアの語る言葉に耳を傾けるうちに神を確信するファットたちであった。やがて、ファットは、自らがディックであったことを想起することに成功する(統合失調・精神分裂・記憶喪失の治癒:主人公ホース・ラヴァー・ファットは、作者フィリップ・K・ディック自身であると明示され、この『VALIS』という小説自体が、ディックの自叙伝じみたものであるというメタ構造が明かされる〉)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%B9_(%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BBK%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
「キラキラ」を通じてニュータイプを真理に触れさせる、という意味では、「ヴァリス」における「神」とジークアクスにおける「シャロンの薔薇」は、同様の意味を持った舞台装置だと言えるでしょう。
ジークアクスでは「シャロンの薔薇」以外にも、マチュのスマホへのメッセージや、カネバン有限公司のハロ、赤いガンダムのサイコミュなど「ヒトを導く機械」が多数登場します。「ニュータイプを真理に導く」という舞台装置としての役割を見ると、これらはすべて一括りの存在だと考えることもできます。その最大のものが「シャロンの薔薇」である、という解釈はどうでしょうか。
「シャロンの薔薇」の正体は?
「シャロンの薔薇」の正体については、ファンの間でも様々な考察がなされています。
- 聖書の「シャロンの薔薇」:砂漠地帯の「森」=理想郷の象徴
- ギリシャ神話の「シャロン」:三途の川の渡し守=この世とあの世をつなぐもの
- サザビーのコックピットブロック:逆シャアとの関連を示すもの
- 『Gのレコンギスタ』に登場する「ヘルメスの薔薇」の設計図:時代を超えてテクノロジーを届けるもの
ゼクノヴァと同様、劇中で「シャロンの薔薇」がどんなものか明確に示されるかどうかははわかりません。曖昧なまま終わる可能性も十分にあると思っていますが、私が考えている仮説についてご説明します。
サイコミュ技術の異常な発達
そもそも、サイコミュなど劇中のニュータイプ関連技術は、元々の「機動戦士ガンダム」と比較すると異常な発達を示しています。本来サイコミュは小型化が難しいためにエルメスなどのMAに搭載されたはずが、赤いガンダムにビットとともに搭載されています。また、ファーストガンダムでシャリアが登場したブラウ・ブロが複座式・62.4mなのに対して、ジークアクスで登場したキケロガは単座式・32.0mと小型化しています。
ゼクノヴァと同等の現象であろうアクシズ・ショックの発生には、サイコフレームが必要なはずでした。当然、1年戦争の時点ではそれは開発されてはいないはずです。このように「本来の歴史であるファーストガンダムよりも、ニュータイプ関連技術の発達が著しい」という点が強調されています。
ニュータイプ技術の発達は、歴史にも大きな影響を与えています。シャアがガンダムを奪取しただけでは、戦局全体への影響は軽微であり、結局ジオンは地球から撤退することになっています。ソロモン会戦までは大局的に変化はなく、従来のファーストと同様の歴史を辿っています。
戦局の逆転は以下の要因によってもたらされました:
- ジオンのMS開発計画の大幅な変更
- フラナガン機関によるニュータイプ研究の進展(シャアを中心に)
- シャアによるガンダムのビットを使用した連邦艦隊への泊地攻撃
特に注目すべきは、ニュータイプの力が戦局を覆したという点です。なぜこのような変化が生じたのでしょうか?
シャロンの薔薇はニュータイプ技術+AI
私はこうした変化は、シャアが奪ったガンダムからもたらされた「教育型コンピュータ」による影響でによってもたらされたのではないか、と考えました。
地球連邦軍系のモビルスーツに搭載されている学習機能を有するコンピュータ。電子回路ではなく光結合回路(GMO)を使用した非ノイマン型コンピュータであり、ミノフスキー粒子の特殊電磁場効果の影響を受ける事はない。ニュータイプの持つ先読み能力を理論化した「先天的行動予測理論」を取り入れており、パイロットの意図を汲み取って挙動を選択する。学習型コンピュータ、INC(推論型ナビゲーション・コントロール)とも呼ばれている。
https://gundam.wiki.cre.jp/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
ここからは私の想像ですが、
- ガンダム経由でジオンにも教育型コンピュータの技術が渡る
- フラナガン機関でサイコミュと組み合わせた教育型コンピュータの技術が研究される
- グラナダの地下で「サイコミュ+教育型コンピュータ」の技術を用いたAIスーパーコンピュータ=シャロンの薔薇が開発される
という経緯を辿ったのではないか、と考えています。
教育型コンピュータは、ファーストガンダムのラストではアムロがセットした無人操作によってガンダムを動かし、シャアのジオングを撃墜する「ラストシューティング」と呼ばれる印象的なシーンを演じました。
もしそれが「シャロンの薔薇」に使われているなら、同様に扱う人がいなくても与えられた目的に対して自動的に動作する「AIスーパーコンピュータ」のような作りになっているのではないかと予想しました。
生成AIは現代の易経
「高い城の男」では、易経が人々を導く役割を果たしましたが、これを現代社会に置き換えると生成AIが果たしている役割に似ています。文章などで調べたいことや、知りたいことの情報を入力し、それに対する答えが出力される、という流れは易による占いの流れと共通点が多いです。
そのため、鶴巻・榎戸両氏は「高い城の男」を元ネタにガンダム作品を作るにあたって「易経の役割を生成AIに置き換えたら面白い」と考えたのではないかと予想します。
「シャロンの薔薇」は歴史を動かしている?
「高い城の男」では、多くの人々が意思決定を易経に依存しています。ジークアクスでも、マチュの行動をサポートするハロのように「機械」が人の意思決定を促すシーンが多数見受けられます。イズマコロニーでマチュとニャアンの出会いを導いたのは1件の謎の電子メッセージでした。これらはどちらも「機械による働きかけがきっかけで事態が大きく動いた」ことを示すシーンです。
私は、これら「劇中の重要な意思決定を導くイベントの多くは「シャロンの薔薇」の影響によって引き起こされている」と考えています。たとえば、シャアが起こしたゼクノヴァは「シャロンの薔薇」が「グラナダにソロモンが落下して自身が破壊されることを恐れて引き起こした」と考えたら辻褄が合います。
「高い城の男」「ヴァリス」の作品構造
この仮説の意味するところをもう少し掘り下げるために「高い城の男」と「ヴァリス」の作品構造について考えてみましょう。
まず「高い城の男」は次のような構造になっています。
- 「フィクションの世界」で暮らしている人々がいる
- 「真理」に触れ「フィクションの世界」の縛りを脱し「自由」を得る人々が登場する
- 主人公(のひとり)はそこが「フィクションの世界」であることに気づく
加えて、劇中で真実とされる「イナゴ身重く横たわる」の歴史は、我々が知る現実の歴史とは細部において異なっています。そのため「現実世界もまた『偽りの歴史』である」「読者に向けて『あなたも作中の人々同様、この世界=現実社会の様々な縛りから解き放たれ、自由になるべきだ」というメッセージが込められていると言えます。
ジークアクスのストーリー予想
また「ヴァリス」では、
- 人々は「真理」に触れ自由を得る
- それは「神」の如き存在による導きであった
- その結果、主人公はそこが「フィクションの世界」であることに気づく
という展開を経ています。どちらも「作中世界がフィクションであると登場人物が気づく」という点に共通点があることに注目です。
先に挙げた「高い城の男」と「ヴァリス」の作品構造をひとつにまとめてみると次のようになります。
- 「フィクションの世界」で暮らしている人々がいる
- 「真理」の導きによって「フィクションの世界」の縛りを脱し「自由」を得る人々が登場する
- それは「神」の如き存在による導きであった
- その結果、主人公はそこが「フィクションの世界」であることに気づく
(太字は「高い城の男」と「ヴァリス」共通)
私はジークアクスのストーリーもこれと同じ構造になっているのではないかと予想しています。
「高い城の男」「ヴァリス」の作品構造と、ジークアクスのそれが一致していると仮定した場合、どんなストーリーの流れが考えられるでしょうか。
ジークアクスの舞台は作中作の世界?
「高い城の男」と「ヴァリス」には、作中世界がフィクションであるというメタ的な構造が含まれていました。素直に解釈するなら「ジークアクスの舞台もフィクションの世界である」ということになります。
それを暗示するかのようなシーンが劇中でも描かれています。後半パートが始まり、マチュが初めて登場するシーンです。マチュは電車の中で「Let’s get the begining(さあ始めよう)」という謎のメッセージを受け取りました。私には、このメッセージがまるでオンラインゲームにログインしたときのウェルカムメッセージのように感じられました。
先に述べたように「ヴァリス」では「神」の導きを受けた主人公が「自分がその世界=小説の作者であったことに気がつく」という展開があります。これと同様に、マチュもストーリーの中で「この世界全部が偽物」という事実に気がつくシーンが描かれるのではないでしょうか。
そのように考えると、マチュが「平穏なコロニー暮らしの日常を、どこか偽物のように感じていた」という設定の意味合いも違って見えてきます。地球とコロニーとを比較して「本物・偽物」と対比させ、彼女の海(地球)への憧れを示す設定であったはずが「そもそも、世界すべてがフィクションであることを暗示していた」という解釈に変わってくるからです。
鶴巻監督が本作をパラレルワールドとは言わず「架空戦記」という表現で語っていることも、ひとつの裏付けになります。現在は創作の世界においてマルチバース/パラレルワールドなどの設定が使われることは珍しくありません。ジークアクスの世界も「ジオンが連邦に勝った世界線」という表現をしている人が多いと思います。
しかし、物語が丸ごと「フィクションの世界」である(と劇中で示される)ということを前提とすれば、そういった解釈も不要になります。
「主人公」を失った世界
「ヴァリス」では、主人公が「神」から啓示を受け、自分が「その小説世界の作者」であることに気がついた後、さらに興味深い描写があります。宗教団体が作った「神」は事故により亡くなってしまい、主人公が得られていた超感覚は失われてしまう、という展開です。
ソフィアの誕生で、ヤルダバオト・デミウルゴス・狂った神といった象徴で語られる古い偽神による支配の時代(黒き鉄の牢獄の時代)が終り、千年王国(ヤシの木の庭園・黄金の時代)が訪れる……かに思われたが、致命的な事故が起きる。
団体員のうちの一人が、ソフィアの額に高出力ビームを照射し脳髄ごと焼き殺してしまう。VALISからの情報出力をより確かなものにしようとした果ての事故であった。ディックたちは、命からがら団体から逃げ出すが、いつしか、すべてが夢であったかのように神や救済の予感は霧散してしまう。唯一と思われた救世主ソフィアの喪失の傷は深く、いつしかディックは、またファットに分裂してしまう。もとあった陰鬱な日常が物語を包む。何も起きない孤独な部屋の中、テレビの前に座り、ファットはまんじりともしなかった。ただ待ち続けた。ただ待ち続けた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA%E3%82%B9_(%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BBK%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%B0%8F%E8%AA%AC)
私がこの展開を知ったときに最初に思い出したのは「ゼクノヴァによるシャアの消失」でした。ジークアクス世界が大きく変わる最初のきっかけは、シャアの「ひらめき」によるものです。ガンダムの奪取からゼクノヴァまで、シャアが歴史を動かしていたといっても過言ではありません。しかし、その途中のアクシデントでシャアは世界から消えてしまうことになりました。「ヴァリス」の展開と非常に似ている印象を受けます。
ジークアクスはハルシネーションによって誕生した世界?
ジークアクスの世界が「作中作」であるとしたら、マチュがいる世界が何らかの物語となっている「外側の世界」がある、ということになります。シャアがゼクノヴァ時に語っていた意味深なセリフ=「向こう側からきたというのか」という言葉も、そのことを意味していたと考えることもできます。「外側の世界」がどのようなものかについては「キラキラ」の劇中での位置づけがヒントになります。
「キラキラ」については、すでに以下のことを示しました。
- 「キラキラ」は「物理現象を伴うもの」として描かれることが鶴巻監督から明言されている
- 「キラキラ」は、Zガンダム以降の宇宙世紀ガンダムで描かれた「全体」との関連が見られる
- 「全体」とはニュータイプがアクセスできる場で、死者の残留思念が集まっている
- ニュータイプは「全体」とつながることで「他人の既知の伝播」や「刻」が見える体験をする
また、「キラキラ」には「ハルシネーション(幻覚)」という物理現象としての名前がつくことが鶴巻監督より明言されています。ハルシネーションとは、本来生成AIの領域で「AIが作り出すでたらめな出力」を指す言葉です。
ハルシネーション (英語: hallucination)、または幻覚(げんかく)、でたらめ[1][2]、作話(さくわ、英:confabulation)[3]、ディルージョン(妄想、英:delusion)[4]とは、人工知能によって生成された、虚偽または誤解を招く情報を事実かのように提示する応答のことである[5][6][7][8]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3_(%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD)
それをあえて「ニュータイプ同士の感応」を表す用語として使用している(そして、それが物理現象を伴うことが明言されている)ということは「ニュータイプの感応によって事実かのような偽物の情報が提示される」と、暗に示しているように思われます。
「シャアの残留思念」がジークアクス世界を生んだ?
これらのことから、私はジークアクスの世界は「逆襲のシャア」のアクシズ・ショックによって誕生した世界ではないか、と考えています。アクシズ・ショックによって、アムロとシャアは「全体」とつながったはずです。彼らの生死は不明ですが、彼らの残留思念(思惟)が「全体」とつながり、それによって「新しい世界が誕生したのではないか」と解釈しました。
この場合、前編パートは「逆襲のシャア世界のシャア(とアムロ)によって生み出された世界」ということになります。ここでいう「世界を生み出したシャア」=「逆襲のシャア」に登場したシャア・アズナブル(以下CCAシャア)のことであって「ジークアクス劇中のシャア」とは別の存在です。
新たに生み出された「ジークアクス世界」のシャアはガンダムを奪い、ライバルのアムロはMSに乗ることはありません。ガルマの命を奪うこともなく、戦況はジオンに有利。シャリアという友人も得て、あまりにもシャアに都合の良い展開ばかりが続きますが「そもそもCCAシャアの残留思念に基づいて世界がつくられた」と考えれば不思議はありません。
おそらく「ジークアクス世界のシャア」を導きながら「ヒトの革新」をもたらそうと干渉していたのではないでしょうか。見方によっては「アクシズ・ショックを起こしたシャアが異世界転生して、自分に都合の良い展開で無双している」とも言えます。
「異世界転生」の主人公がいなくなった世界
しかし、ここでアクシデントが起こりました。第二次ソロモン会戦の際、シャアが生き埋めとなり、脱出できなくなってしまったのです。そこで「サイコミュ+教育型コンピュータ」のAIとである「シャロンの薔薇」が(おそらくは、自分本来の任務であったグラナダ防衛のために)ゼクノヴァを起こしたのではないか、というのが私の解釈です。
「逆襲のシャア」のアクシズ・ショックで、アムロとシャアが消失してしまったのと同様、ゼクノヴァによって「ジークアクス世界のシャア」も消失してしまいました。その後のジークアクス世界はいわば「主人公がいなくなった世界」ということもできます。
「シャロンの薔薇」に受け継がれたシャアの意思
シャアの喪失により「ジークアクス世界」は「ヒトの革新」をもたらすために必要な主人公を欠いた状態になりました。しかし「シャロンの薔薇」はゼクノヴァを起こした際、シャアと感応を起こして「他人の既知の伝播」が起きていたはずです。(シャアも「刻が見える」と明言しています)
このとき「ジークアクス世界のシャア」の残留思念が「シャロンの薔薇」に伝播し、その目的が「ニュータイプによる新しい時代を作ること=ヒトに革新をもたらす」に変わったのではないでしょうか。そのためにグラナダの地下から「シャロンの薔薇」は姿を隠し、おそらくは地球に身を隠しつつ、人知れず人々のニュータイプへの覚醒を導いている、というのが私の仮説です。
この解釈を取る場合、ストーリーの中で何かを「探している3人のキャラクター」の目的が、すべて「シャロンの薔薇」という一つのものに集約されるのでストーリー上のまとまりが非常に綺麗になります。
マチュ:本物・自由を求めている
シュウジ:シャロンの薔薇を探している
シャリア:シャアを探している
そして、この「シャロンの薔薇」のお眼鏡に叶ったのがマチュだったのではないでしょうか。もちろんマチュだけでなく、シャリアを始め、それ以外のニュータイプに対しても干渉し、導きを与えているはずです。「ヒトの革新」をもたらすために、様々な登場人物を思うがままに誘導し、自分が思い描いたストーリーに導こうとしているのではないでしょうか。
前半パートと後半パートは別の世界?
私の解釈では、前半パートは「逆襲のシャアのアクシズ・ショックで起きたハルシネーションによって生じた世界」となります。ハルシネーション(ニュータイプ同士の感応現象)は、新しい世界を作り出す、という仮説です。
その場合、第二次ソロモン会戦で起きたゼクノヴァもまたハルシネーションであり、それによって生じた世界が別にあるのではないか、という解釈が成り立ちます。私はジークアクスの後半パートは「前半パートのゼクノヴァによって生じた、前半パートの世界のさらなる作中世界」ではないかと考えています。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』のおかしな点に「前半と後半でまったくキャラクターデザインが異なる」という点があります。
しかし「前半と後半で、世界そのものが変わっている」と考えれば、キャラデザの変更はむしろその伏線になっていた、と読み取ることもできます。
「マルチバース内で、ゼクノヴァが起こるたびに別のパラレルワールドへと世界線が切り替わる」という表現のほうが伝わりやすいかもしれません。
「創られた世界」の違和感に気づくマチュ
私は、後半パートがスタートし、マチュが謎のメッセージを受け取った瞬間こそが「あの世界が誕生した瞬間」なのだと考えています。ソロモンにおけるゼクノヴァによって、直接的に「その5年後の世界」が生じたのか、1年戦争終了後からの5年間に別のゼクノヴァがおきたのかはわかりませんが、「後半パートの世界(ジークアクス本編)」の世界が誕生したのはあの瞬間からではないかと考えています。
登場人物はもちろん、それ以前の記憶もありますが、それらはすべてそのように「設定された状態」で世界がスタートしたからだと思います。ちょうど、RPGなどのゲームを最初から始めたときに、バックグラウンドとなる前置きのストーリーはすでに存在しているのと同じです。
「シャリア・ブルのように、前編・後編の両方の登場する人物」も多数いるはずですが、それらについても同様です。彼らはあくまで「前編シーンの時系列に相当する、自分の過去の記憶」を持っているだけであって、世界が誕生した瞬間に「すでにその状態でできあがっていた」と考えます。
また、「作中世界の動き出した現実」と「設定上の記憶に登場する人物」のキャラクターデザインが異なっていてもおかしなことはありません。当然、作中の登場人物には同じように見えているはずなので、彼らが違和感に気づくこともないはずです。
このように考えると、マチュがシャアの写真を始めてみたとき「変な仮面」といったことにも、深い意味があるように解釈できます。マチュは「創られた世界」の違和感に気がついているため、常識で考えれば明らかに「変な仮面」を被っている人に違和感を覚えたのではないでしょうか。
マチュはジークアクスに選ばれた?
ここまで考えたときに「マチュはなぜシャロンの薔薇に導かれる対象として選ばれたのか?」という理由が判然としませんでした。同時にもう一つの謎として残っていたのが、主役機であるジークアクスの存在です。おそらく機体名の「GQuuuuuuX」は「9番目のガンダム」といった理由なのでしょうが、何をもっての9番目なのかという点がわかりませんでした。
逆に「ジークアクスの存在と、マチュが選ばれた理由がイコールではないか」と考えると、自分の中でピースがつながったような感じがしました。つまり「シャロンの薔薇」ではなくMS・ジークアクスが「ヒトの革新をもたらす存在」としてマチュを選び、導いているのではないか、という仮説です。
「シャロンの薔薇」が「教育型コンピュータ+サイコミュ」であるならば、ジオンは戦後もその研究を続けていたはずです。ジークアクスにはオメガサイコミュが搭載されていますから、それらの研究も踏襲しているのは間違いありません。「シャロンの薔薇」のテクノロジーが組み込まれた「9番目のガンダム」がMS・ジークアクスである、と考えるとすべてがつながってきます。
ジークアクスが「シャロンの薔薇」の干渉を受けるなどして、自身の教育型コンピュータでも「ヒトの革新をもたらすこと」を目的として設定したならば「そのために最適なパイロットを探す」という行動原理でマチュに干渉したとしても不思議はありません。
赤いガンダムも、同じような理由で同じく自ら選んだパイロットであるシュウジを「シャロンの薔薇」の元まで導こうとしている、と考えたらどうでしょうか。
ジークアクス・今後の展開を予想
「高い城の男」や「ヴァリス」のストーリー、そしてガンダム長年のテーマである「ニュータイプ」や「ヒトの革新」・・・これらを下敷きとして、今後のTVシリーズの展開を予想してみたいと思います。
地球には行くが、期待していたような自由・本物の感覚は得られない
マチュはコロニーでの暮らしが偽物、地球が本物だと考えています。だからこそ地球に憧れ、行きたいという意思を示していることが特別映像でも語られています。
しかし、作中世界がすべて「ハルシネーションで生まれた偽物」なのであれば、地球に行っても彼女の満足は得られないでしょう。
「ニュータイプ能力の喪失」から逆転劇が描かれる?
ニュータイプに関する解釈を説明した部分で、鶴巻監督が描きたい「ヒトの変革」は「自らの意思で変わろうとすれば、ヒトは変われる」「それを実践できる存在がニュータイプ」ということではないかと説明しました。そして「それを実践できるのであれば、特殊能力の有無は関係ないのではないか」という仮説も立てました。
鶴巻・榎戸作品である「フリクリ」では、特殊な能力に目覚めた主人公が登場しますが、彼に近づいてくる女性たちは能力や立場など、彼の人格以外の部分に惹かれている、という描写があります。主人公が彼女たちに「どうやって自分自身の人格を見てもらうか」という点が物語の一つのテーマでした。
また「トップをねらえ2!」においては、特殊な能力によって重宝されていたヒロインが、その能力が不要になったために、世の中から見向きもされなくなる、という展開が描かれます。結局、ヒロインは能力ではなく「努力と根性」によって状況を打開することになります。
ジークアクスにおいても、これと同様の展開が描かれるのではないでしょうか。マチュ、あるいはその他の登場人物がニュータイプ能力を失い、それによって挫折を経験するものの、その後の能力が戻る・戻らないに関係なく「変わろうとする意思」によって事態を打開する、という展開になると予想します。
ラストは「本当の世界」への脱出となるか?
マチュが求める「本物」の本質的な意味とは「シャアなど特定の人の思念によって歪められていない世界」であると考えられます。それは「ジークアクス世界」の外側にしかありません。
したがって、マチュの目的はMS・ジークアクスの導きに従い「シャロンの薔薇」を探す、そしてシュウジとともにゼクノヴァを起こすことになると予想します。
実際、鶴巻監督は過去に別の作品で「現実世界への脱出」を描いています。鶴巻氏が同じく監督を務めている「シン・エヴァンゲリオン劇場版」における、主人公のシンジが現実世界(実写)に行く、とうラストシーンです。
物語は最後、成長した姿のシンジと成長したマリが駅のホームで交流し、マリがDSSチョーカーを外し、そしてシンジがマリの手を取り、駅から飛び出していくというラストシーンでエンドロールへと移ります。
駅のホームを出ると人物以外が実写になるのですが、ここで映されるのが庵野秀明氏の出身地である山口県の宇部新川駅。まさに全てのエヴァにさよならを告げたシンジ達が、新たな世界=現実の世界へ飛び出していくという、希望が感じられるラストカットでした。
https://note.com/syuririn/n/ncc2c00bc6d75
この描写は、同作の総監督を務める庵野秀明氏が好きな作品として挙げている「幕末太陽傳」の「幻のラストシーン」からの影響が伺えます。「幕末太陽傳」は時代劇作品であるものの、ラストで「その外側」にある世界への脱出を描いてしまおう、という案が存在していました。
脚本段階では、上記のラストシーンに続き、墓場のセットが組まれているスタジオ(と観客に分かる状況)を佐平次が走り抜け、さらにスタジオの扉を開けて外に飛び出し、タイトルバックに登場した現代(1957年)の品川へ至り、そこにそれまでの登場人物たちが現代の格好をしてたたずみ、ただ佐平次だけがちょんまげ姿で走り去っていく、という案があった(採用されなかった経緯は下記)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%82%B3
上記の「幻のラストシーン」は、川島雄三がかねてから抱いていた逃避願望および、それとは相反する形で佐平次に託した力強さが時代を突き抜けていくことを表現する、本作を象徴するシーンになるはずだったが、演出があまりに斬新すぎたために、現場のスタッフやキャストからは「意味が分からない」と反対の声が飛び出した。川島が自らの理想像とまで見なしていた佐平次役のフランキー堺まで反対に回り、結局現場の声に従わざるを得なかった(フランキー堺は後年「あのとき監督に賛成しておくべきだった」と語っている)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E6%9C%AB%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%82%B3
これは「積極的逃避」とも表現されますが、シン・エヴァンゲリオン劇場版では、これと同様のことが描きたかったのではないかともされています。
「偽物」ならではの良さを肯定する
しかし「エヴァ」のラストは庵野氏の意向が強く表れていると考えられるため、鶴巻氏がこの点についてどう捉えているのかはわかりません。その点を推測するには、鶴巻氏の「フィクション」に対する捉え方を確かめる必要があります。
全体的に『フリクリ』は、荒唐無稽なアニメーションの魅力とカタルシスに溢れており、生々しさやリアリズムを追求した『エヴァ』とはかなり異なる作風だ。鶴巻監督は、自身と庵野とのアニメーションに対するスタンスの違いを以下のように語っている。
鶴巻 庵野さんは、アニメが嘘であることが許せないっていうか、そこにコンプレックスを抱いてる。僕にはわからない感覚なんだけど。庵野さんや貞本さんは、アニメにどれだけリアルを投入できるかに力を注ぐんです。 <中略> でも、僕はそうじゃなくていいと思っている。今石君(筆者注:今石洋之)の描くような荒唐無稽なアクションも大好きだし、それを抑制することで失われてしまうパワーが惜しい、と感じてしまう。(※1)
https://news.yahoo.co.jp/articles/1bc311a48cd06d74f23fdbd760db2b82c87d5a58
この鶴巻氏の「フィクションに対するポジティブな考え」は、ジークアクスにも間違いなく表れてくると考えます。ですので、ジークアクスのラストは「エヴァ」とはまったく逆の展開になるのではないでしょうか。つまり「マチュは『本物』を手に入れられる状態で、あえて自分の意志で『偽物の世界』を選ぶ」という選択をするのではないか、と予想します。
終わりに:ジークアクスは何を伝えたい作品なのか?
以上の私の予想全体を、もう少しメタ的な視点で捉えてみると「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」という作品は、ガンダムというアニメづくりに取り組むクリエイター論である、という捉え方もできます。
たとえば「逆襲のシャアによってジークアクスの世界が生まれた」という解釈は、「逆襲のシャアを見て育ったクリエイターが、新しいガンダム作品を作った」と捉えることもできます。
従来の宇宙世紀ガンダム作品では、後年の作品になるほどネガティブに描かれがちだったニュータイプを「ポジティブなものとして描きたい」というのは鶴巻監督自身の発言です。「過去のガンダム作品と対比して、自らの考えで新しい解釈を吹き込む」という点についてはすでに決意表明があるわけです。
そのうえで私が考えるラスト「本物よりもあえて偽物を選ぶ」という点は、アニメがフィクションであることを肯定的に捉える鶴巻監督ならではの主張になる、と予想します。
鶴巻監督が「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」を通じて伝えたいこと、それは、
将来を含めて自分以外の「ガンダムづくり」に取り組むクリエイター(あるいは全てのクリエイター)に対して、
- リアリティがなくたっていいじゃないか
- 既存の設定を無視してもいいじゃないか
- 何者にも縛られず自由に、面白いと思えるものを作ろう
という創作に関する想いではないでしょうか。
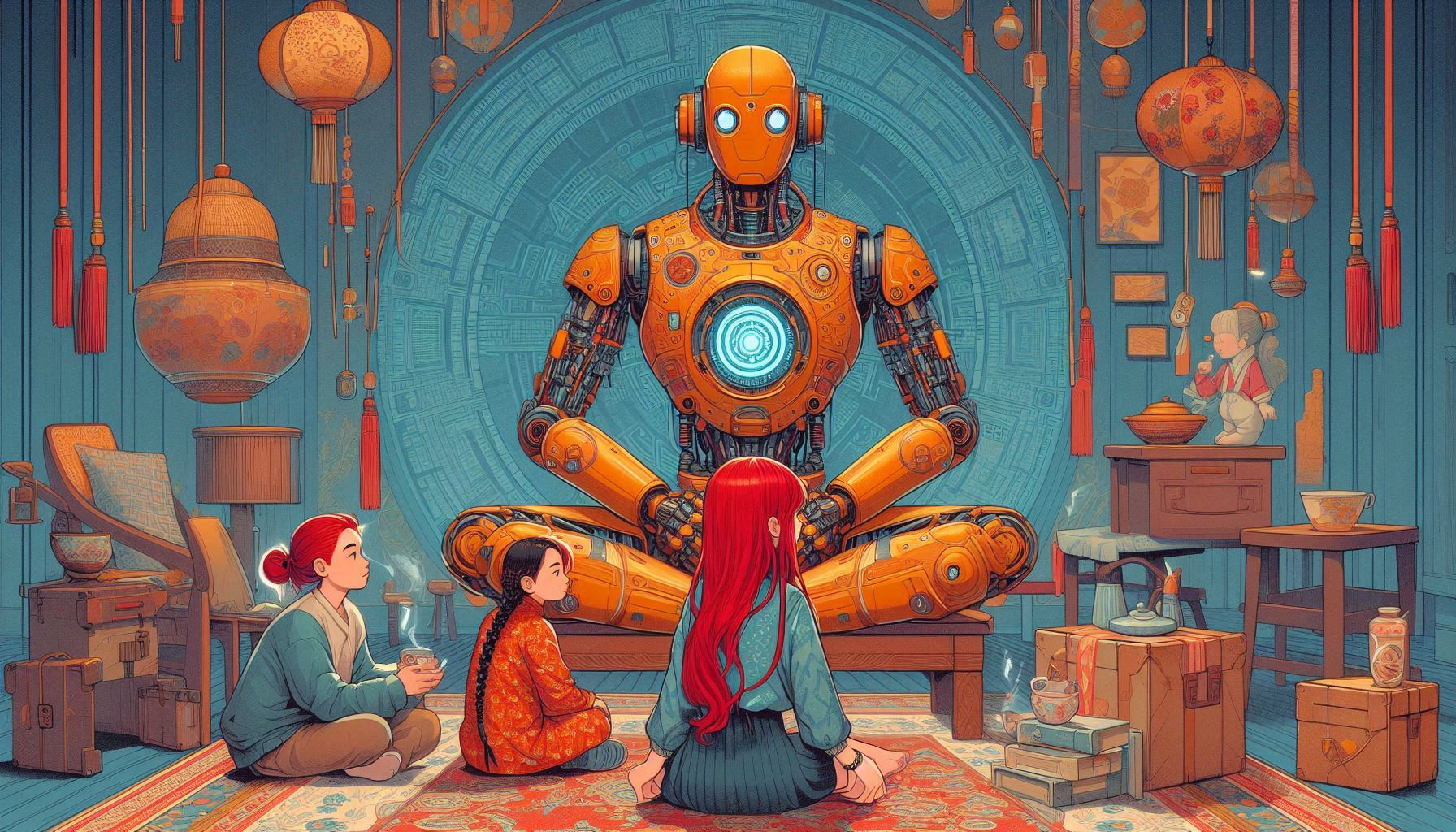
じっくりと最後まで拝読しました。締めが、いい。
ありがとうございます!