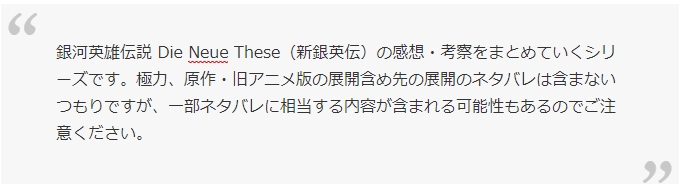
3話「常勝の天才」
~少年キルヒアイスの思い出~
ある日、幼いキルヒアイスの家の隣に貧乏貴族の一家が引っ越してきた。翌朝、キルヒアイスは隣家の一員である金髪の少年「ラインハルト・フォン・ミューゼル」とその姉、アンネローゼと出会う。キルヒアイスはラインハルトと打ち解け、アンネローゼを含めた3人で過ごすひとときは彼らにとって幸福な時間になっていった。
しかし、幸せな日々は長くは続かなかった。アンネローゼが皇帝に見初められ、後宮に入ることになってしまったのである。アンネローゼは別れの日、「ラインハルトのこと、頼むわね」という言葉と、ケルシーのケーキを残して2人の元を去っていった。
その後、姉を取り戻すことを望むラインハルトは、早く一人前になろうと幼年学校に入学。姉を取り戻すため幼年学校に入学。軍人となり、早く一人前になることを志す。
「僕と一緒に行こう。一緒に姉さんを取り戻すんだ」
そうラインハルトに誘われたキルヒアイスは、アンネローゼと最後に交わした言葉を思い出しながら、差し出された手を力強く握った。
オーベルシュタインの言動が疑われた理由
今回取り上げるのは、キルヒアイスの過去の回想シーンです。そもそも、なぜこのような回想に入ったのか、その導入に当たるシーンを先に振り返っておきましょう。
前回取り上げたシーンは、「キルヒアイスとオーベルシュタインの出会い」でした。オーベルシュタインはキルヒアイスの前で帝国の始祖・ルドルフ大帝の批判を行いましたが、キルヒアイスはそのことで彼に警戒心を懐きます。後でラインハルトと2人きりになったところでオーベルシュタインを「得体の知れない男です」と評しているのがその現れです。
ラインハルトも「敵が多いから用心しておくに越したことはない」とキルヒアイスの見方に賛成しました。このシーンの直前には、オフレッサーやほかの将校たちなど、ラインハルトを妬むものが多いことを示す描写が描かれています。彼ら自身もそのことには気がついており、自分たちに嫉妬・反感の念を持つ連中を「敵」と認識していることが確かめられたわけです。
つまり、彼らはオーベルシュタインもまた「敵」の仲間であり、自分たちから何らかの失言を引き出すためにわざと体制批判的な発言を行ったのではないかと疑っていると解釈できます。
「星空」は何かの象徴
ここで2人の会話は、急にプライベートなものになりました。「明日姉に会いに行く」というラインハルトが、キルヒアイスも一緒に行こうと誘っているのです。このときのラインハルトの表情は非常に柔らかなもので、戦場で見せた冷静な表情とはまったく違うものでした。
厳密に言えば、ラインハルトはこうした優しい表情を唯一、キルヒアイスと一緒にいるときには浮かべています。つまり、話の中に登場したラインハルトの姉、ラインハルト、キルヒアイスには、なにか精神的に特別なつながりがある、ということが示唆されているわけです。
問題の回想シーンでは、3人のつながりとはどのようなものなのか具体的に描写されるわけですが、その導入はキルヒアイス自身による次のようなナレーション(独白)から始まります。
あのころ、星空は私にとって遠いものだった。
決して手が届かないもの。手を伸ばそうとすら思ったことのないもの。
それが変わったのは・・・。
この中で出てくる「星空」とは、現実の星空のことではなく、キルヒアイス(とラインハルト)にとっての何かを象徴するものだと解釈できます。それが具体的に何なのかは後のストーリーの中で明らかにされてきます。
キルヒアイスとミューゼル姉弟との出会い
いよいよ今回の本題である回想の中身に迫っていきましょう。
回想は、幼少期のキルヒアイスが、隣の家に引っ越してきた貧乏貴族の一家=ラインハルトの家族と出会うところから始まります。キルヒアイスは父・母との3人家族、ラインハルトは父・姉との3人家族です。
朝、学校に行こうとしていたキルヒアイスは、ラインハルトとの初対面を果たします。このときのラインハルトは現在のような冷静な目ではなく、少年らしい優しさ・純真さを称えた瞳をしていました。
注目するべきは2人の初会話の内容でしょう。子ども同士が初めてであったわけですから、当然お互いの名前を名乗り自己紹介をするわけですが、ラインハルトはキルヒアイスの名前(ジークフリード)を聞くなり、「俗な名前だ」と馬鹿にするような発言をしています。
キルヒアイスも一瞬、リアクションに困ったような表情を見せますが、ラインハルトは続けて「でも、キルヒアイスって姓はいいな。とても詩的だ」と褒め、これからは姓で呼ぶことにすると言いました。少年キルヒアイスはまたしても反応に困っている様子でしたが、これはラインハルトの「生まれながらの性格」を表す演出でしょう。
相手の名前の良し悪しを評価するというのは、初対面の会話としてはセンシティブな内容です。ですが、まだ純心な子どもであればたとえ悪意がなかったとしても、相手が気を悪くするという可能性さえ考えずに、このような発言をしてしまう場合もあるでしょう。つまり、ラインハルトは思ったことをすぐに口に出してしまうような「純真・真っ直ぐな性格である」ということが描写されているのです。
キルヒアイスはラインハルトに続いて、彼の姉であるアンネローゼとも出会います。このシーンはキルヒアイスの顔が赤くなり、声も大きくなっていることなどから描きたいことは明白でしょう。「少年が年上のきれいなお姉さんに憧れと恋心をいだしてしまう」という、アニメや漫画などでありがちな場面です。
ただし、アンネローゼが(おそらくは何気なく)キルヒアイスにかけた「ジーク、弟と仲良くしてやってね」という言葉は、物語上重要な意味を持つことになるので、よく覚えておいたほうがいいでしょう。
3人で過ごす、短くも幸せな日々
ラインハルトはキルヒアイスと同じ学校に入学し、同じクラスになりました。しかし、校内には彼を快く思わないものもいるようで、ラインハルトは上級生に呼び出され、リンチを受けそうになってしまいます。
クラスメイトが、ラインハルトの名前にある「フォン」の文字に反応したことや、上級生が「生意気な貴族様」と彼を揶揄したことからもわかるとおり、ラインハルトが一部の生徒から反感を買ってしまったのは彼の家が貴族であったからというのが主な理由でしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3_(%E5%89%8D%E7%BD%AE%E8%A9%9E)
フォン(独:von) は、ドイツ語の前置詞。英語の前置詞フロム (from) またはオヴ (of) に相当する。
この前置詞は、ドイツ語圏(オーストリアなどを含む)において、しばしば王侯(フュルスト)・貴族や準貴族(ユンカー)の姓の初めに冠する称号として使われる。
つまり、貴族の子どもなのに、貴族の子弟だけが通うような学校に入ることができない=金銭的な余裕がない、というラインハルトの家計事情が示されるとともに、「貧乏なのに生まれだけで自分たちとは身分が違う存在である」という、一般庶民の貴族に対する反感が同時に描かれているわけです。
キルヒアイスはラインハルトが上級生に呼び出されたという話を聞くと、すぐさま彼を助けにむかいます。このことからも、キルヒアイスは貴族という身分に別段偏見を抱いていないことがわかります。彼の父も、隣に引っ越してきた一家について息子が「貴族のように(金持ちのようには)見えない」と語ったとき、「貴族といってもいろいろだ(金持ちとは限らない)」とソフトな形で伝えており、両親の教育のおかげで貴族への偏見が育たなかった可能性もあるでしょう。
ラインハルトが複数人の上級生をいかにして撃退したのか、劇中では詳細に描かれてはいません。しかし、キルヒアイスが現場に駆けつけたとき、ラインハルトが手から石を投げ捨てている様子が確認できるので、ものを握って拳を固くし、パンチの威力を上げていた可能性はあるでしょう。おそらくラインハルトはこういった喧嘩はもう慣れっこで、有効な撃退方法を習得していたのだと思われます。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216870267
ラインハルトは、喧嘩をしたことがアンネローゼにバレて悲しませてしまうのを危惧しますが、ここでキルヒアイスが助け舟を出しました。噴水に落ちたことにして制服を濡らしてごまかすというアイデアを思いつき、ラインハルトと一緒に自分までびしょ濡れになったのです。秘密を共有したことで、2人は無二の親友となりました。
キルヒアイスがラインハルトと仲良くなったのは、たまたま家が隣同士だったということと、好意を抱いた彼の姉から「弟と仲良くしてほしい」と頼まれたのがきっかけです。しかし、キルヒアイスは周囲から敵意を向けられてもひるまず、それを真正面からはねのけていくラインハルトの意志の強さに尊敬の念を抱いたのではないでしょうか。同じように、ラインハルトも自分に対して常に誠実に接してくるキルヒアイスの優しさに好感を持ったはずです。2人が友人になったのは偶然でしたが、仲良くなったのは「ウマがあったから」だと言えるでしょう。
ラインハルトとキルヒアイスにアンネローゼを加えた3人は、短いながらも幸せな日々を送っていました。アンネローゼはラインハルトにとっては「最愛の姉」、キルヒアイスにとっては(おそらく)「初恋の人」であり、彼らと同様にアンネローゼも2人のことを愛おしく思っていたはずです。
苦難にあったときのラインハルトとキルヒアイスの違い
アンネローゼは引越し後、間もなく後宮に入ることとなり、2人の元を去ってしまいますが、どのようにして皇帝に見初められたのか、本作では描かれていません。また、ラインハルトの父親も描写が少ないため、娘を手放すことについてどのように思っていたのか性格には不明です。ラインハルトは「父が姉を皇帝に売った」と語っていましたが、本当にお金に困って娘を手放したのか、それとも皇帝から強要されて従わざるを得なかったのか、あるいはその両方が原因なのかは劇中の描写だけでは判然としません。
おそらく、話の本筋とは関係がないために描写が省略されたのでしょう。実際、この場面で重要なのは「ラインハルトとキルヒアイスが、それぞれ姉と初恋の人を失った」という事実です。この場面は回想ですから、キルヒアイス(もしくはラインハルト)から見た事実だけを描写していたのかもしれません。困窮であろうが強権による抑圧であろうが、意に沿わぬ形で大切な人を奪われてしまったことは、少年2人にとって大きな心の傷になったはずです。
キルヒアイスは後宮に行くアンネローゼを何もいえずに見送るしかありませんでした。別れの日にもらったケルシーのケーキを見つめながらうつむくさまは、姉の後宮行きを知ったとき、涙を流しながらも怒りに震えていたラインハルトとは対照的です。耐え難い苦境に陥ったとき、キルヒアイスは感情を表に出さずにじっと耐える性格であり、ラインハルトは感情を発露しながらも打開策を考える性格であるという、2人の違いがわかりやすく現れています。
幼少期に体験した衝撃的な出来事
姉がいなくなった後、ラインハルトはキルヒアイスに何も伝えずいずこかへ消えてしまいました。しかし、まもなく再びキルヒアイスの前に姿を表し、幼年学校に入学したことを告げます。これまで、この少年の日の回想がいつのことなのか、具体的な年月を示す描写はありませんが、「幼年学校」に関する情報からある程度推測することは可能です。
ドイツ(プロイセン)に習って作られた、旧・日本軍の陸軍幼年学校は、受験資格が満13歳~となっています。本作の舞台ははるか未来ですが、普遍的な歴史の偶然・必然を描くのがテーマの作品なので、幼年学校の入学規定といった物語の本筋と無関係な部分は、ほぼ現代に近いものが踏襲されていると考えていいでしょう。ここから推理すれば、ラインハルトとキルヒアイスが出会ったのは、10歳前後の出来事だったと推定できます。なお、原作では、10歳のころと明確に示されています。
キルヒアイスが決断した理由は、愛でも友情でもない
キルヒアイスはラインハルトの誘いに乗り、軍人となって出世しアンネローゼを取り戻すことを決意しました。しかし、彼はなぜそのような決断を下したのでしょうか?普通に考えれば、いかに「初恋の人を失う」という衝撃的な出来事を経験したとはいえ、後宮に入った女性を取り戻すなど簡単にできることではありません。
このときのキルヒアイスの心情を考える手がかりになるのが、最後にアンネローゼから渡されたケルシーのケーキを見ながら、悲しみに暮れるシーンです。姉を奪われたラインハルトの怒りに震える表情が正面からアップで映されたのに対して、このときのキルヒアイスは背後から映され、どんな表情をしているのか描かれていません。なぜこのような描写がされたのか、その理由を探ることがキルヒアイスの気持ちを考えるヒントになります。
アンネローゼ、そしてラインハルトがいなくなった後、キルヒアイスは日常に戻りましたが、このときの彼の表情は気の抜けたような、なんとも言えないものでした。彼の表情に生気が戻るのは、再びラインハルトと再会し、「軍人にならないか」と誘われたときです。
その瞬間、キルヒアイスの脳裏にかつてアンネローゼから言われた「ラインハルトのこと、頼むわね」という言葉がフラッシュバックしました。彼がラインハルトの提案のみ、力強く手を握り返したのはこのときです。これは、キルヒアイスの胸に、ずっとアンネローゼが言葉が引っかかっていたことを意味します。
おそらくキルヒアイスは、アンネローゼと別れてから、初恋の人の最後の頼みにどのようにしたら応えられるかずっと考えていたのでしょう。ところが、頼むと言われた対象であったラインハルトまでもがどこかへ言ってしまったため、何もすることができなくなってしまったのです。
そこで気が抜けたように過ごしていたところで、思わぬ形でラインハルトと再会し、彼から「自分と一緒に軍人になってほしい」と頼まれたわけです。キルヒアイスにしてみれば、ずっと心に引っかかっていた「初恋の人の頼み」に応える方法がようやく見つかった心地だったことでしょう。
キルヒアイスがラインハルトの突拍子もない提案に乗ることを決断したのは、彼が初恋の人を忘れられない純粋な子どもだったからでも、ラインハルトとの友情を特別に思っていたからでもありません。短いながらも充実した幸せな日々を送っていた彼は、突如としてそれを奪われ、ぽっかりと心に穴が空いたような状態になってしまいました。どうしたらその状態を解消できるか、唯一の手がかりだった「初恋の人の最後の願い」に自問自答を繰り返し日々を過ごしていたのです。ラインハルトの提案は、彼にとってずっと抱えていた心のしこりを取り除く最後のピースだったと言えるでしょう。
